1. DX戦略の策定
デジタルガバナンス・コード3.0は、企業価値向上のためにDX戦略の策定を極めて重要な要素と位置付けています。
1-1. 目的と経営者の役割
DX戦略の主たる目的は、データとデジタル技術を活用し、企業が目指すビジネスモデルを実現することです。これは、経営ビジョンを達成するための中核的な戦略であり、経営者自らが強力なリーダーシップとコミットメントを持って主導すべきです。
DXへの投資は、単なるコストではなく、企業の未来に向けた不可欠な投資であるという認識が重要です。
1-2. 戦略の要点
DX戦略の策定には、以下の点が不可欠です。
- デジタル技術を経営資源と捉える:
経営陣は、データを価値を生み出す重要な資産として認識し、データに基づいた意思決定を日常的に実践する必要があります。 - 「両利き経営」の視点:
既存ビジネスの効率化・高度化と、新規デジタルビジネスの創出を両立させます。これは、既存事業の深化(効率化)と新規事業の探索(創出)を同時に進める「両利き経営」の視点であり、持続的な成長に不可欠です。 - 戦略の公表とコミュニケーション:
策定したDX戦略は機関承認を得て公開し、経営ビジョンや成果とともに「価値創造ストーリー」としてステークホルダーに開示することが求められます。この透明性は、社内外の協力と期待を高める重要な戦略となります。
1-3. 継続的な評価
DXは継続的なプロセスです。企業は達成度を測る具体的な指標を定め、定期的に自己評価を行う必要があります。評価結果は、事業部門やITシステム部門の現状分析とともに、戦略の見直しに反映されます。
2. DXを推進する組織づくり
デジタルガバナンス・コード3.0は、DX戦略の実行を支える強固な組織基盤の構築を重視しています。
2-1. 組織横断的な体制の構築
DXを成功させるには、IT部門だけでなく、事業部門や経営企画部門など、関係部署が密接に連携する組織横断的な体制が不可欠です。このような体制は、DXを全社的な取り組みとして位置づけ、各部門の役割と責任を明確にします。また、自社内のリソースだけでは限界があるため、外部アドバイザーやスタートアップとの連携など、オープンイノベーションを積極的に活用することも推奨されます。
2-2. 予算と役割の明確化
DX戦略を推進するためには、DXのための予算を他のIT予算とは別に管理することが推奨されます。これにより、DX投資が短期的な投資収益率(ROI)に縛られず、中長期的な視点での挑戦を促進できます。また、経営者から現場まで、各人が主体的に動けるよう役割と権限を明確にすることが望まれます。
2-3. 組織文化とマインドセットの変革
DXでは技術導入だけでなく、人の意識と行動の変革が鍵です。新しい挑戦を促し、社員一人ひとりがデジタル技術を活用するマインドセットを醸成するための仕組み作りが重要です。具体的には、以下のような取り組みが有効です。
- 行動指針の策定・公開:
社員が仕事のやり方や行動をどう変えるべきかを示します。 - 実践的な人材育成:
役割に応じた研修を実施し、社員が集まるコミュニティを形成して、デジタルリテラシーを向上させます。 - 挑戦を推奨する文化:
失敗を許容し、積極的に挑戦する組織文化を醸成します。
3. DXセレクション選定企業の実践事例:株式会社後藤組
経済産業省が選定する「DXセレクション」企業は、デジタルガバナンス・コード3.0の精神を具体的に体現する優れた事例です。グランプリに選ばれた株式会社後藤組の事例は、DX推進の成功要因を明確に示しています。
3-1. 現場主導のDXと新規事業創出
後藤組のDX戦略は、現場業務の徹底したデジタル化にあります。特に注目すべきは、ノーコード・ローコードツール「kintone」を活用し、現場社員自身が業務アプリを作成・改善するアプローチです。これにより、紙ベースの業務がアプリに移行され、残業時間が大幅に削減されました。
さらに、余剰資材を再利用するアプリを開発するなど、DXが環境貢献とコスト削減を両立させる具体例も生み出しています。また、自社で培ったDXのノウハウを他社に提供する「DX支援事業」も検討しており、DXをコストセンターからプロフィットセンターへと変える可能性を示唆しています。
3-2. 全員参加の組織づくりと人材育成
後藤組の組織づくりは、トップダウンとボトムアップの戦略的な融合が特徴です。
- トップダウン:
導入当初の抵抗を打破するため、社長の指示で全社員に簡単なアプリの使用を義務付け、利用習慣を形成しました。 - ボトムアップ:
その後は「デジタルの民主化」を掲げ、現場の主体性を引き出しました。 - 人材育成:
DXスキル向上のための「DXワークショップと大会」、社内資格制度を導入し、実践的な学びと知識共有を重視しました。特に「勉強会で最も成績の悪かった社員が次回講師を務める」というユニークな仕組みは、社員の主体的な学習意欲を喚起しています。
これらの取り組みは、新卒社員の定着率を大幅に向上させるという具体的な成果につながり、DXが人的資本経営に貢献する好例となっています。
4. DX推進を成功に導くための提言
デジタルガバナンス・コード3.0が示す指針は、企業がDXを戦略的かつ持続的に推進するための重要な道しるべです。DXセレクション選定企業である株式会社後藤組の事例は、これらの指針をいかに現場で具体的に実践し、有効な成果につなげたかを示しています。
4-1. 経営層の強いリーダーシップとビジョン
コードが求める経営層のコミットメントは、DX推進の成否を分けます。後藤組では、社長自らが全社員に日報アプリの使用を義務付け、DX推進の突破口を開きました。この行動は、社員の抵抗を乗り越え、DXが全社的な取り組みであることを明確にしました。
- 提言:
経営層はDXを単なるIT施策ではなく、企業価値向上と競争優位を目指す経営変革と位置付け、明確なビジョンと戦略を策定し、全社に浸透させる強いリーダーシップを発揮すべきです。
4-2. データとデジタル技術を経営の中核に据える視点
DXはデータとデジタル技術を経営資源と捉え、意思決定に活用することが不可欠です。後藤組は、建設現場の紙ベースの業務をアプリ化することでデータを蓄積し、残業時間や資材コストの削減という具体的な成果を生み出しました。このように、日々の業務から生まれたデータを活用するアプローチは、現場の課題解決だけでなく、経営全体の効率化にも貢献します。
- 提言:
企業は、データの収集・管理・分析能力を強化し、経営判断から現場業務まで、全社的にデータドリブンなアプローチを徹底すべきです。
4-3. 組織文化の変革と人材育成
DXは技術導入だけでは成功しません。後藤組は「デジタルの民主化」を掲げ、社員自らがノーコードツールで業務アプリを開発する仕組みを構築しました。さらに、「勉強会で最も成績の悪かった社員が次回講師を務める」というユニークな制度で、社員の主体的な学習と知識共有を促しています。
- 提言:
DXには技術導入にとどまらず、人の意識と行動、組織文化の変革が不可欠です。実践的な育成プログラムや、挑戦を促す文化を醸成し、組織全体のDX推進力を高めるべきです。
4-4. 外部連携とオープンイノベーション
コードは、自社にない知見や技術を外部から取り込むオープンイノベーションを推奨しています。後藤組は、自社で培ったDXのノウハウを「DX支援事業」として他社に提供することを検討しています。これは、DXの成果を自社内にとどめず、外部へ価値提供する新たなビジネスモデルであり、DXをコストセンターからプロフィットセンターへと変える可能性を示唆しています。
- 提言:
自社に不足する知見や技術を補うため、外部の専門家やスタートアップ、他企業との積極的な連携を通じて、新たな価値創造とDXの加速を図るべきです。
4-5. 継続的な評価と戦略の見直し
DXは一過性のプロジェクトではなく、継続的なプロセスです。後藤組は、紙の使用量や残業時間など、具体的なKPIを設定してDXの効果を客観的に評価し、その結果を基に戦略を見直す改善サイクルを回しています。
- 提言:
明確なKPIを設定し、定期的に進捗と成果を評価・分析し、市場や技術の変化に応じて柔軟に見直すアジャイルな姿勢が不可欠です。
5. まとめ
デジタルガバナンス・コード3.0は、企業がDXを通じて持続的な成長と企業価値向上を実現するための羅針盤です。その中心には、「DX戦略の策定」と「組織づくり」という二つの柱があります。
DX戦略では、IT導入にとどまらず、データとデジタル技術を経営資源として活用し、既存事業の深化と新規事業の創出を両立させる「両利き経営」の視点が求められます。経営層の強いリーダーシップのもと、戦略は明確な指標と価値創造ストーリーとして社内外に発信され、企業価値向上への期待を高めます。
組織づくりでは、トップダウンの推進力と現場の自律性を融合させることが重要です。DX予算は他のIT予算と分けて管理し、経営に不可欠な投資として位置付けることで、中長期的な挑戦を支える環境を整備します。さらに、組織文化の変革と人材育成を通じて、社員一人ひとりがデジタルリテラシーを高め、自律的に変革を推進するマインドセットを醸成することが不可欠です。
これらの原則を体現しているのが、DXセレクション選定企業である株式会社後藤組の事例です。経営層のコミットメント、現場を巻き込む仕組み、継続的な学習と改善など、事業特性に応じた実践がコードの指針と合致しており、多くの企業にとって参考となる実践例です。
- 第1回記事:中堅・中小企業のデジタル変革を促進する経済産業省の取組とDXセレクション2025受賞事例
- 第2回記事:なぜかあまり知られていない「DX認定制度」をやさしく解説 ~DXに立ち向かうのなら、この制度を活用しよう~
- 第3回記事:DXセレクション2025グランプリ受賞事例(株式会社後藤組)とデジタルガバナンス・コード3.0
- 第4回記事:デジタルガバナンス・コード3.0の概説と「経営ビジョン・ビジネスモデル策定」の重要性
- 第5回記事:デジタルガバナンス・コード3.0: DX戦略の策定と組織づくり(本記事)
- 最終回記事:DX認定取得に向けた平均的なタイムラインとDX支援ガイダンス
筆者
 |
経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 地域情報化人材育成推進室長・デジタル高度化推進室長 河﨑 幸徳 |
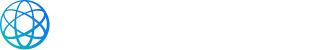

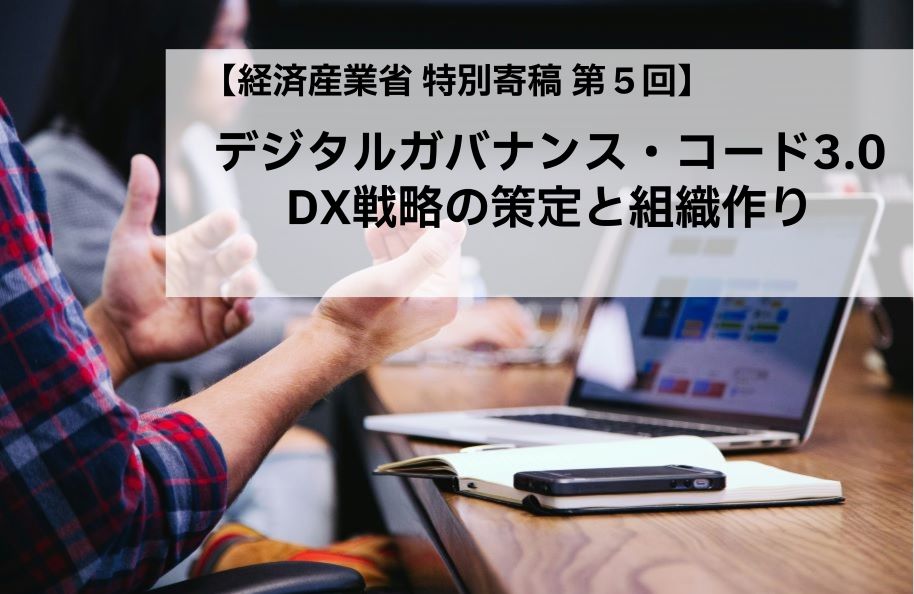




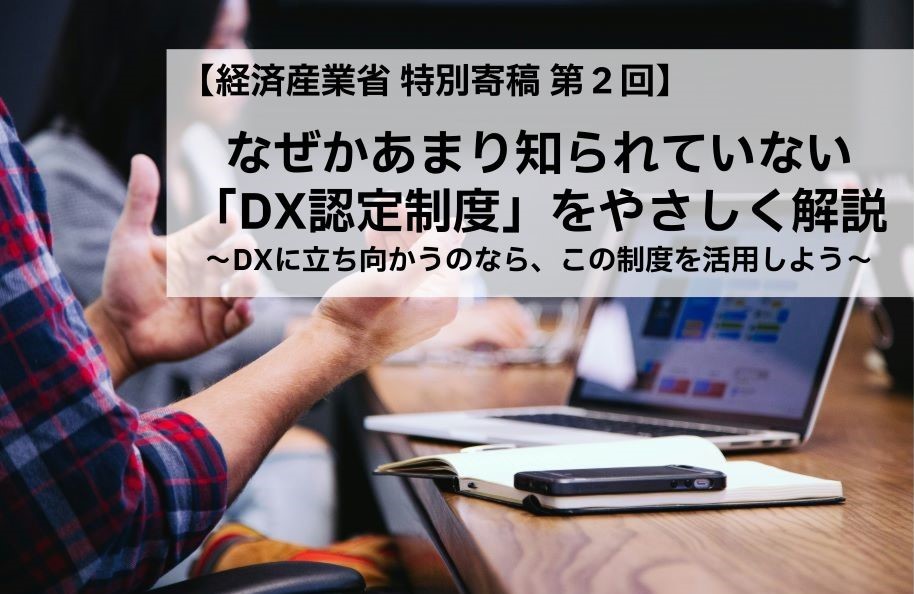
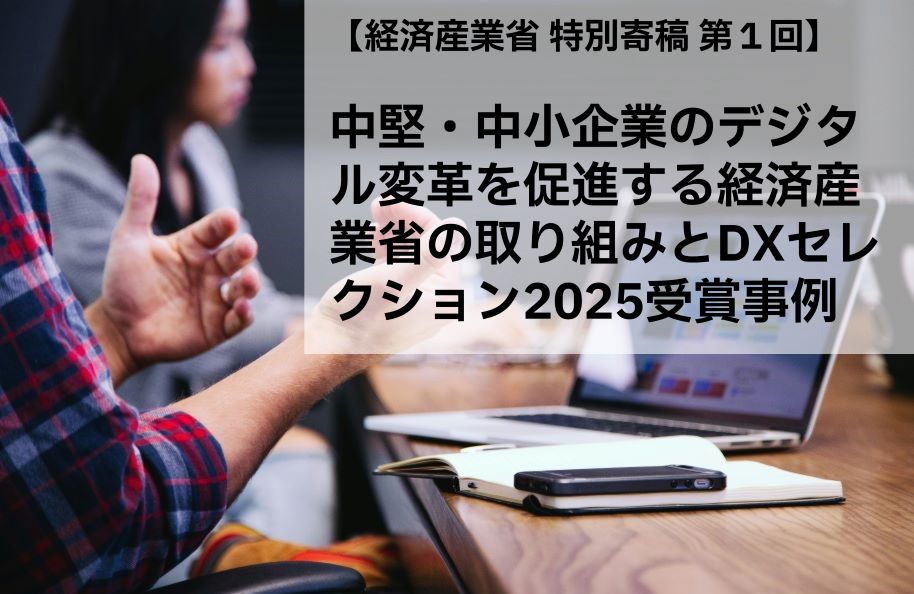
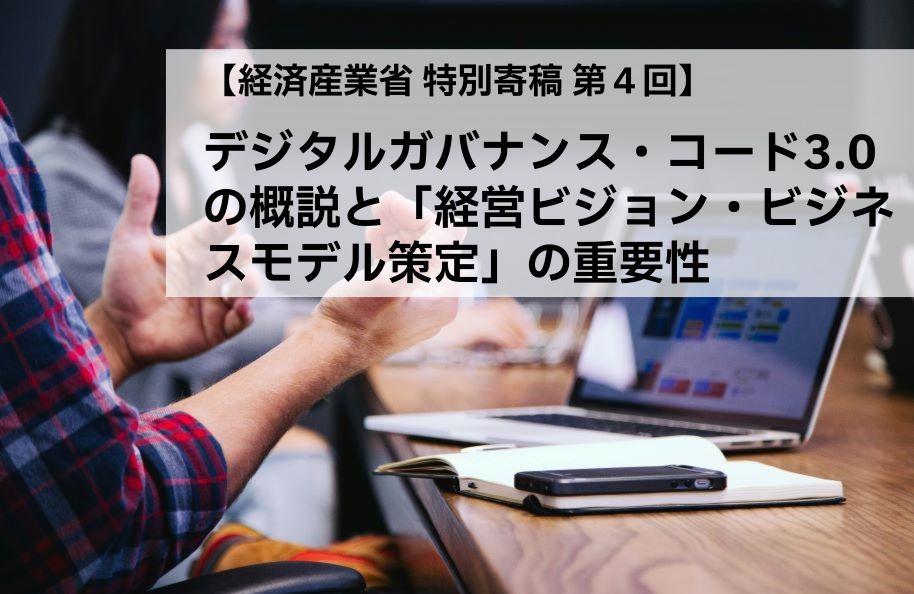
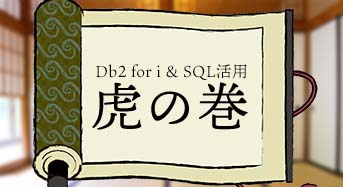
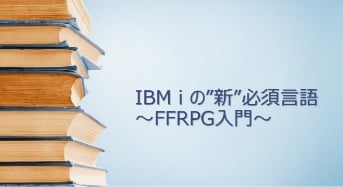

はじめに
経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード3.0」は、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を経営の中核に据え、企業価値を向上させるための指針です。このコードは、IT導入にとどまらず、デジタル技術を経営資源と捉え、組織全体を根本的に変革することを目的としています。
DX推進は、短期的な収益だけでなく、以下のような多岐にわたるメリットを生み出します。
特に、労働人口が減少する日本において、DXは優秀な人材の確保・育成・定着に直結する重要な戦略です。したがって、DXは中長期的な企業競争力の源泉として位置付け、投資家を含むすべてのステークホルダーに対し、「価値創造ストーリー」として語るべき包括的な経営戦略です。
今回は、コードが示す「DX戦略の策定」と「組織づくり」の要点を掘り下げ、経済産業省が選定した「DXセレクション」企業の事例から、成功要因を分析します。
経済産業省 デジタル高度化推進室長 河﨑 幸徳