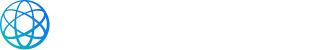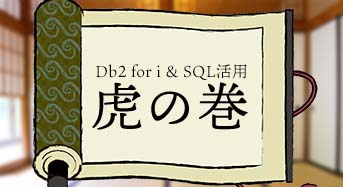連載一覧 Serials
無償で利用できるようになったDb2 for iのSQLパーティション表は、膨大なデータをテーブルに格納し、格納先から条件に基づく効率的なデータの抽出と処理を可能にします。SQLパーティション表の活用方法を対談記事の抄訳ご確認ください。
Db2 for iの内部構造の概要や、Db2 for iがユーザーに代わって実施している複雑で大量の仕事について、Db2 for iの最新機能や歴史的経緯を織り交ぜた対談記事の抄訳で紹介します。
アプリケーションのモダナイゼーションについては、これまでにも連載を組んでお話をしてきました。今回は話題の焦点を「データベース」のモダナイゼーションに絞り、チャーリー・グアリーノと世界的に有名なデータベースの専門家であるビルギッタ・ハウザーの対談の抄訳をお届けします。
地理空間データをビジネスアプリケーションで利用する手法が近年注目されています。IBM i 7.4や7.5にもDb2 for iで地理情報を取り扱うための地理空間関数が追加されています。今回は、地理データと地図情報を組み合わせてビジネスで活用する方法をWeb Query for iを使った例でご紹介します。
前編では、分析データ抽出用のストアドプロシージャの作成とこれを使用するWeb Queryの初期作業について説明しました。後編では、ストアドプロシージャが抽出した表を使ってWeb Queryで分析報告書を作成する例をご紹介します。
ストアドプロシージャを使うことで、既存の表から容易にデータ分析用の仮想的な表を作り出すことができ、簡単に分析レポートを作成することができます。今回は、導入部としてストアドプロシージャの作成方法とそれを利用するWeb Queryの初期作業についてご説明します。
データベース・モダナイゼーションの重要性については、これまでも様々な記事でお伝えしてきた通りです。今回は、その実施に当たってSQLビューを活用することで、リスク、コストを低く抑えつつ、モダナイゼーションの価値を十分に享受できるということをご紹介します。
前回の記事の後編として、配列データ型とそれに関連するSQL関数に関する記事をお送りします。今回は、配列変数と表を相互に変換するための新しいSQL関数を使った処理の例やJavaによる配列パラメータの受け渡し例、SQL配列を使ったプロシージャのデバッグ法など、より実践的な内容を具体例と共にお届けします。
Db2 for i 7.1でサポートされるようになった配列データ型は、SQLやJavaプロシージャと多数のパラメータをやり取りしたいときや、SQLを使って配列のデータをあたかもデータベースの表のように処理したり、逆にデータベースの表を配列データの様に処理したりすることができます。
データの値に応じて実行時にSQL文を動的に変化させることで、SQLの可能性が大きく広がります。今回はSQLのCASE式を取り上げ、データに基づいて実行時にSQL文を変化させることで、どのように便利なことが容易に実現できるのかを例題を使って分かり易く解説します。
最近新たに追加されたSQL HTTP関数の基礎知識をご紹介。今回は具体的にSQL HTTP関数を利用した簡単なAPIの作成例をご紹介します。このテクニックを応用することで、従来RPG言語単独では難しかった処理が他言語を介して容易に解決できる可能性が高まります。
今回取り上げるSQL HTTP関数は、オープンな環境においてIBM iと異種システムとの連携処理を容易に実現し、IBM iの利用価値を高めるものです。最近このSQL HTTP関数に新たな関数が追加されましたので、今回と次回の2回に分けてこの新しい関数の使い方についての解説ブログを掲載します。
データベース定義をDDLで行うべきか、DDSのままで良いかという論争は古くからありますが、適材適所で使い分けるのがベストというのが結論のようです。では、その使い分けの基準はどのようなものなのでしょうか。この記事を読み、DDLとDDSの使い分けについて、自分の会社ではどうあるべきか改めて整理し直してみてはいかがでしょう。