このたび、IBM i の開発拠点であるロチェスター研究所を訪問するツアーに参加して、最新の技術動向や製品アップデート情報を直接確認できました。常に最新リリースの二世代先の計画が公開されているIBM i そのものの他に、短期的にも中長期的にも未発表の情報が多数あり…すなわち、記事に書けない内容が盛りだくさんでした。
そこで、本記事では、現時点で公になっている、IBM i を稼働させるIBM PowerサーバーやIBM Power Virtual Serverを構成する際に参考となる情報や学びに絞って紹介させていただきます。
IBM Power Virtual Serverが仮想シリアル番号をサポートした意味
2023年に発表された「仮想シリアル番号(略称 VSN:Virtual Serial Number)」は、IBM Powerサーバー上の論理区画に対して割り当てられるものです。つまり、シリアル番号がある物理的なIBM Powerサーバー上の論理区画が仮想的なシリアル番号を持つのです。そして、その仮想シリアル番号を前提にIBM i のソフトウェアの注文や転送が行えます。
結果、仮想シリアル番号に紐づく形でIBM i のライセンスなどが存在することから、例えば災害対策用の別のIBM Powerサーバーに該当の論理区画を移動させることが容易になります。
2023年の発表当時、仮想シリアル番号はIBM Power Virtual Server(以後、PowerVS と記述)でサポートされておらず、サポートが開始されたのは本年(2025年)の1月でした。これによって、オンプレミス環境のIBM Powerサーバー間、もしくは同じハードウェア管理コンソール(HMC)の管理下でのみ移動が可能だった仮想シリアル番号が、PowerVSへも移動できるようになったのです。
この仮想シリアル番号のPowerVSでの利用について、参加者向けのセッションの1つであった「Power Update/Power VS and Directions」で、1つの学びがありました。
通常、IBM i を導入する物理サーバーの機械グループによって決まるソフトウェアグループが、PowerVSで仮想シリアル番号を利用する場合には、物理サーバーの機械グループの縛りなくソフトウェアグループを選択できるのです。さらに、各ソフトウェアグループ間の移行がサポートされたため、柔軟に拡張できるようになりました。
物理サーバーの機械グループによって固定的に決められるソフトウェアグループが、PowerVSと仮想シリアル番号の組み合わせでは、お客様による選択が可能となることで自由度が増します。多くのお客様にPowerVSの利用をご検討いただきやすくなる情報を学べたことは、本ツアーでの収穫の1つでした。
IBM Power S1122におけるIBM i の構成の考え方

IBM Power S1122
IBM Power S1122は、IBM Power11プロセッサーを搭載するIBM Powerサーバーの中で、IBM i のプロセッサー(機械)グループが「P10」に分類されている2U筐体の2ソケット・サーバーです。
IBM PowerサーバーでIBM i を構成する場合、VIOS(Virtual I/O Server)を用いる仮想化を前提とする場合が多いのですが、Power S1122については以下の通りIBM i のネィティブ区画もサポートされます。
- IBM i をネィティブ区画でサポート:4コアのeSCM(エントリー・シングル・チップ・モジュール)プロセッサー×2枚構成のみ
- VIOSによる仮想化を前提にIBM i をサポート:10コアのeSCMプロセッサー×2枚、16コア、24コア、30コアのDCM(デュアル・チップ・モジュール)プロセッサー×2枚
IBM i 環境のみを必要とするお客様の場合は、上述の通り4コアx2のプロセッサーカードを選択いただくことになります。一方、VIOSによる仮想化を前提とする形でIBM iを構成する場合は20~60コア(10コア eSCMプロセッサー×2 から30コア DCMプロセッサー×2)の間で選択肢と拡張性が広がります。
今回のツアーに参加した成果の1つは、VIOSを用いた完全仮想化の際に構成面で考慮するべき点を、ロチェスター研究所の担当者に直接確認できたことです。そして、この結果、VIOS + IBM i + Power S1122を的確かつ幅広くお客様に検討いただけるよう、システム構成の作成方針が明確になりました。
実は、Power S1122固有の考慮点として、VIOSによる仮想化を前提にIBM i を構成する場合、CPUとメモリー以外の全てのハードウェアリソースをVIOSから仮想的に割りあてる必要があるのです。結果、Power S1122と組み合わせて使用するNVMeデバイスやテープ装置の選定に際して、仮想SCSIや仮想ネットワークなどからの割り当ての可否を考慮する必要が生じます。(Power S1122以外のモデルでは、IBM i 区画にネイティブにハードウェアリソースの割り当てができます。)
本件でお客様にご迷惑をおかけすることがないように、国内関係者と連携してまいります。
ハードウェアとソフトウェアの両輪で強化されるAI機能
IBM Powerのハードウェアは、Power10プロセッサー搭載サーバーの時点で、AI処理アクセラレーターであるMMA(Matrix Multiply Accelerator)をCPUコアに搭載していました。そして、既報の通り、Power11プロセッサー搭載サーバーでは、オフチップのAIアクセラレーターである「IBM Spyre」の発表が今後予定されています。
一方、本記事で内容を紹介することはかないませんが、IBM i の各ソフトウェアもAIとの親和性を高めるとともに、強化されたAI向けの機能の実装が進められていく方針が紹介されました。ちなみに、本年4月に発表済みであるIBM i のイベント監視ソフトウェアである「Manzan」は、すべてのシステム・イベントを業界標準のApache Kafkaのトピックに取り込めるので、AIスタック(AIアプリケーションの構築、トレーニング、デプロイ、運用、管理を連携して行うためのツール、テクノロジー、フレームワークの集合体)やプログラムは取り込んだシステム・イベントをリアルタイムで分析できます。
将来的に、お客様がご利用のPowerサーバーで未使用のコアをAI関連の区画へ割りあてるなど、検討いただける選択肢の広がりを期待して、今後のAI向け機能強化の発表を待ちたいと思います。
ラボ・ツアーで確信した2U筐体の奥行の寸法が変化した意味

入り口左上に「DANGER」と書かれている落下試験室
スタディー・ツアーの初日には、ラボ・ツアーが組み込まれており、製品の実験やテスト環境の施設を見学させていただきました。
ラボでは、低温、高温多湿、落下テスト、騒音テストなど、実際の使用環境を想定した厳しい試験が行われており、各試験が再現性の高い設備のもとで実施されている点からも品質管理への徹底した対応を実感いたしました。
ところで、皆様はPower10プロセッサー搭載サーバーから2U筐体の奥行の寸法が変化していることにお気づきでしょうか?
実は、Power9プロセッサー搭載サーバーで28インチだった奥行が、Power10プロセッサー搭載サーバーでは32インチに変化しています(Power11プロセッサー搭載サーバーの2U筐体も同様)。

さまざまな検証機が格納されているラック
ラボ・ツアーでは、解体ショーのごとくサーバーの内部構造も拝見させていただき、安心してお客様にご検討いただけるシステム装置であることを確認いたしました。
そして、サーバーを格納するラックの選定に影響することではありますが、Power10プロセッサー搭載サーバー以降の2U筐体の奥行は、サーバーを構成するコンポーネントが最適な性能を発揮するように配置するうえで必要なサイズであることを確信しました。
今後に向けて
このたびIBM i の開発拠点において最新の技術動向や製品アップデート情報を直接確認できたことで、今後、IBM i をお客様に提案およびご検討いただくにあたり非常に有益な知見が得られました。
また、AIとIBM i の連携について学べたことは、大変貴重な機会となりました。
今回の学びを活かし、構成作成担当者として、より一層IBM i の価値をお届けできるよう取り組んでまいります。
関連情報
筆者
|
|
株式会社イグアス |
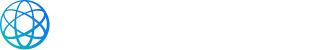

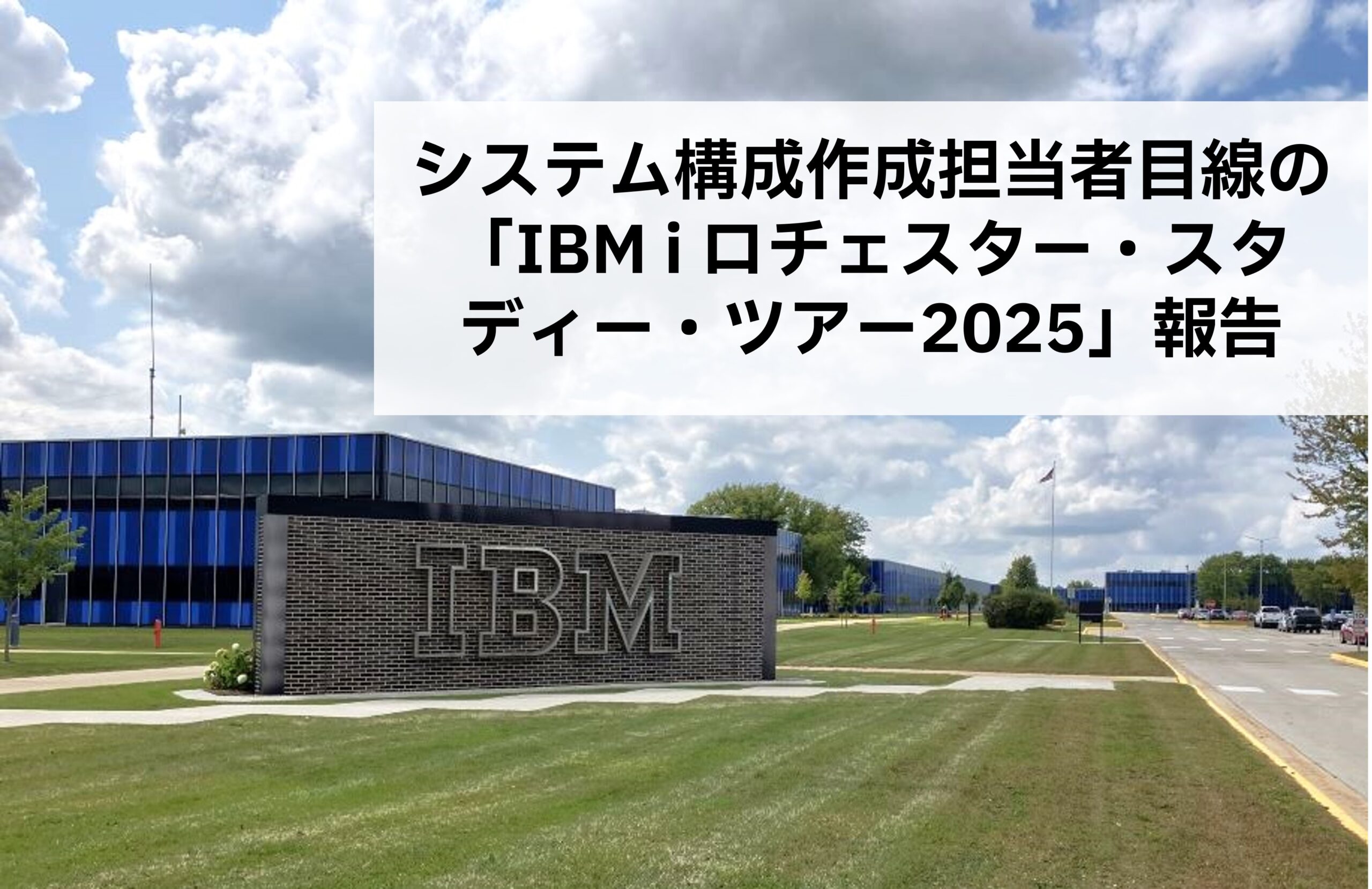







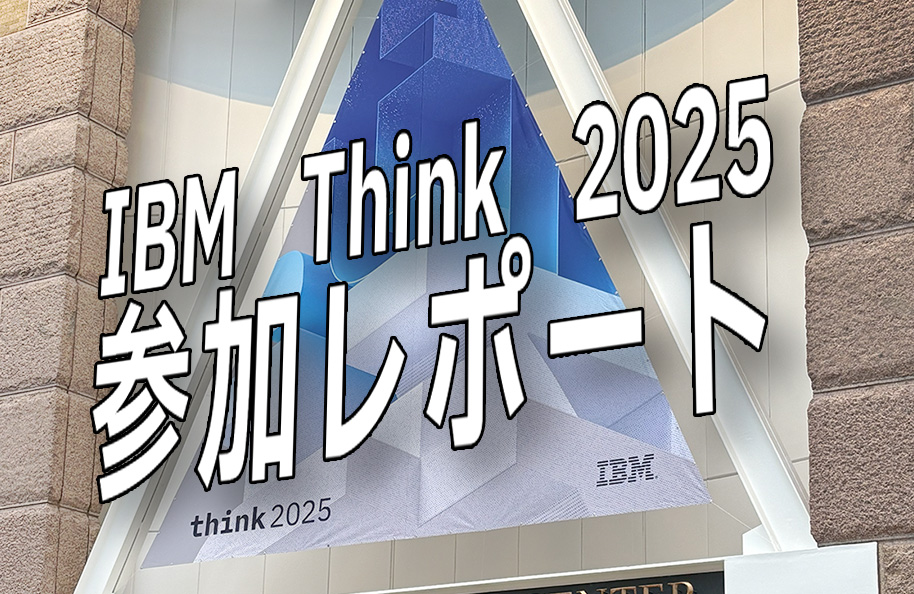
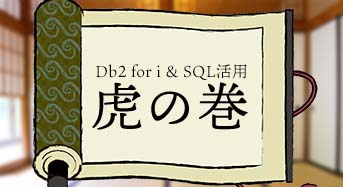
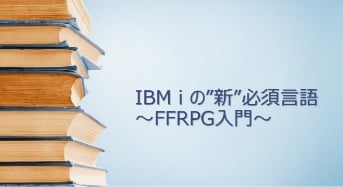

日本アイ・ビー・エム株式会社のIBM Power事業部が2023年から再開した「ロチェスター・スタディー・ツアー」では、IBM i の開発総本山である米国IBMのロチェスター研究所を訪問します。IBM i の開発の現場を目の当たりにすることで、「IBMは、IBM i に積極的に投資をしていて、将来も大丈夫」と認識できる構成となっています。
2025年の同ツアーは9月に開催され、株式会社イグアスからはIBM Powerサーバーなどのシステム構成の作成を担当している山中喜則が参加しました。山中によるシステム構成作成担当者目線の報告記事をご一読ください。(編集部)